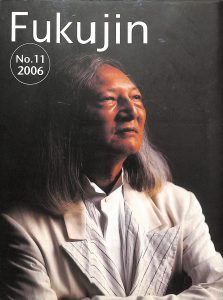原理としてのマゾヒズム<家畜人ヤプー>の考察:安東泉・・・『血と薔薇』1969年 No.4より
「ヤプー本質論」中において、ポーリンとクララの交わす論談は示唆的である
『家畜人ヤプー』第五章「ヤプー本質論」中において、ポーリンとクララの交わす論談は示唆的である。「奴隷だって人間です」とクララは弁護する。「奴隷は制度の産物で、制度で人間の本質を否定することはできません」。この人権意識の常識が本来のイース国における当り前の常識からは理解できない。ポーリンは答える。「ヤプーは類人猿(エイプ)よ。獣(ビースト)よ、いくら知性(インテリジェンス)があっても、獣を奴隷とはいわないわ、家畜だわ、ヤプーは知性ある家畜なのよ」。こうして、すべての認識や倫理や道徳はもはや何のより所も失ってしまうのだ。何のより所も失わしめてしまった完全失墜のその状況、すべての先入観的な人権意識的人間肯定の倫理主義を、いちおう清算し、御破算にしてしまった地点が、アブノーマル主義における原点であり、「イース国の航時快速艇(タイム・ヨット)は過去の原点と、未来の原点と、その中間の過渡的な”とわれの世紀”とを自由に飛翔できることで”とらわれること”から自由であり得る、あり得ることで自己をとらわれずに解放するのである。それは人間の解体作業といってもいい。人間は解体され、肉便器(ストウーラー)にも極小佚儒(ピグミー)にも、何者にも再生されうる無限の可能性を付与された素材として再認識されるのである。この解体作業において、人間が神に転生し、素材すべてを駆使・支配し得る超人的権力志向型に向うことは、ノーマルな立場である。ノーマルな限り、ついに、真に人間の解体はなされ得ない。<砂の上の植物群>という、サジスチックな縛りもの小説を書いた吉行淳之介氏が、いろんな実験的セクスの在り様に熟知し、大衆宜伝的にPRに努めても、「私はサジスチックな傾向がある、が、結局ノーマルなんだな」と、新聞紙上の雑文中に告白するように、それは氏のみならず、大方の心の底の、ここのところの本音なのである。アフリカ主義と、黒人の女への羨望と、性の生む多様な観念上の実験的世界に執拗な執着を示す大江健三郎氏が、故郷の松山に帰った折り、遊客に地元のポン引と間違われて憤慨し、ひいては松山の街の性風俗の乱れと堕落ぶりを、きわめてノーマルに常識そのものの立場から嘆いてみせる素直さに、ついつい大江氏の、作品中での多様なセクス世界の実験的追究ぶりのその本意のあまりにも無邪気な底の浅さを、はからずもごく些細なところで垣間見せる、といったように、これだけ百花撩乱の異常セクス氾濫のブームが招来される時代の、それでもごくノーマルな健全性において、セクス上の通念は、小揺るぎもせずその根底において、以前と変りはないのである。幼児退行症的未発達な性の薄弱さが、いわゆる壁の中の人間、壁の中の観念過多なセクス上の妄想をふれ上らせていくが、その実証的意志的根拠の裏付においてはまったく薄弱である。
・・・原理としてのマゾヒズム<家畜人ヤプー>の考察:安東泉:『血と薔薇』1969年 No.4より・・・次号に続く