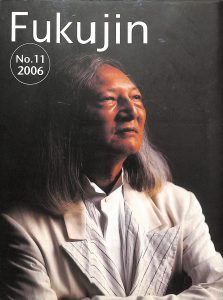原理としてのマゾヒズム<家畜人ヤプー>の考察:安東泉・・・『血と薔薇』1969年 No.4より
鞭の果す効用は、サジズムにおいて不可欠のものであると同時に、マゾヒズムにおいても同時に不可欠な重要な小道具であり得るのか?
さてそこで、鞭の果す効用は、サジズムにおいて不可欠のものであると同時に、マゾヒズムにおいても同時に不可欠な重要な小道具であり得るのか?実は、このあたりに、大きな誤解が生じた。マゾをサドと一括して、苦痛淫愛症(アルゴラグニア)と呼ぶことの定義づけの錯誤が生じた。
誤解を生んだ一半の責住は、マゾの始祖L・F・ザッヒエル・マゾッホ自身にも、ないとはいいきれない面はある。代表作として有名な《毛皮を着たヴィナス》の中でも、迫力を呼ぶのはこうした鞭打場面であった。ヴァンダは右手に鞭を握って立ちはだかり、ゼヴェリンを嘲笑しながら叫ぶ。
「おばかさん。わたしはお前を笑ってやるわ、軽蔑してやる。わたしの玩具になってしまった愚かなお前は、奴隷なんだよ、鞭の味をいやというほど思い知らせてやる」
貂の毛皮の袖をまくったヴァンダは、白い腕を振り上げ、まるでナイフの刃のように鋭い鞭の痛みを、雨と降らせ火と注ぎ、そして笑いながらなお打ちつづけるのである。
鞭打が呼ぶ苦痛からの快感は、マゾッホばかりでなく、初期の谷崎潤一郎の諸短編にも散見されるところである。
「間もなく少女は、なほ先生の裸体の上に腰かけたまま、小さな一本の籐の苔を取り上げ、片手で先生の髪の毛を掴み、片手で先生の太つた臀をぴしぴしと打つた」(『蘿洞先生』)
マゾとは、苦痛を享受するアルゴラグニアであり、鞭と苦痛を媒体とするサドの裏返しの形、という定義づけは、つまりこのあたりから生れた。こうした理解は、しかしサドの側からの理解に過きないようであった。マゾヒストの、マゾの側からの理解ではないことに言及する必要があろうと思う。南極が大陸だからといって、北極が同じく大陸だということにはならない。それは月の表側の地形図に差があるように、マゾヒズムはサジズムの裏側に対照的に存置するのではなく、別の、別次元の、それはそれなりに独立した世界観を背景に踏まえて成立するものである。
・・・原理としてのマゾヒズム<家畜人ヤプー>の考察:安東泉:『血と薔薇』1969年 No.4より・・・次号に続く