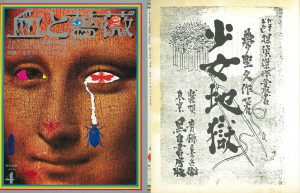「教える」ことの否定
人は自分を教え導いてくれる師というべき存在を本能的に欲する生き物であるらしい。「らしい」と言ったのは、私自身、振り返ってみると、そうした師と呼べる人が見当たらないからだ。
たとえば興行の世界で一世を風靡した神彰との関係がそうかと問われれば、それもちょつと違うのだ。
これは私が「教える」「学ぶ」という関係に特殊な感情や考えを持っているせいだと思う。誰しもが等しく受ける学校教育の出発点からして、私は一方的に「教えられる」ことに対し、ある種の違和感を覚えていた。
人を教え育てるという教育は、ある目的を持ってある鋳型に生徒を流し込むことである。だから、どんなに優れた教育であろうと、どんなに正しく思われる教育であろうと、教育という行為はどこかで個人の人格を無視した暴力的な要素を孕まざるをえないわけだ。そのことに私は敏感なのかもしれない。
私は中学でも高校でも授業中、先生の話をろくに聞かず、勝手に自分で勉強をするような生徒であったが、四、五歳の幼稚園児のころからすでに、先生の教えることを無視したり、勝手な解釈をして自由気ままな振る舞いをしていたらしい。
もの心がつく前から教育というものが放つ暴力性に生理的に身体が反発していたのだと思う。小学校や中学校に上がってからは、すべてはフィクションだ、だから教育だって絶対的なものではないんじゃないかという感性と目線を持っていたような気がする。私は人間はとことん自由な存在であるべきだという本能に近い感覚を生まれつき持っているのだろう。
どんなにいいものであっても押し付けられたものはいい結果を生まないと私は思っている。学びというのは、自発的に選び取っこそいい成果を生むと思っている。
・・・以上、虚人のすすめ―無秩序(カオス)を生き抜け (集英社新書)より抜粋